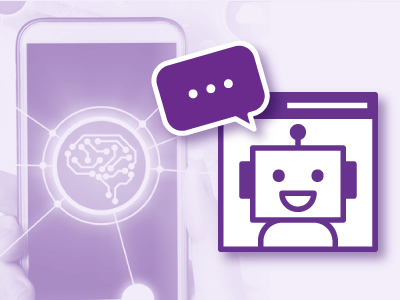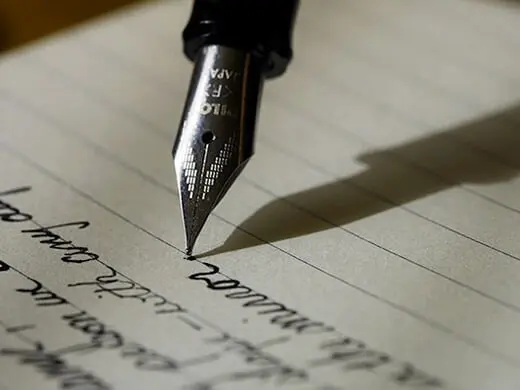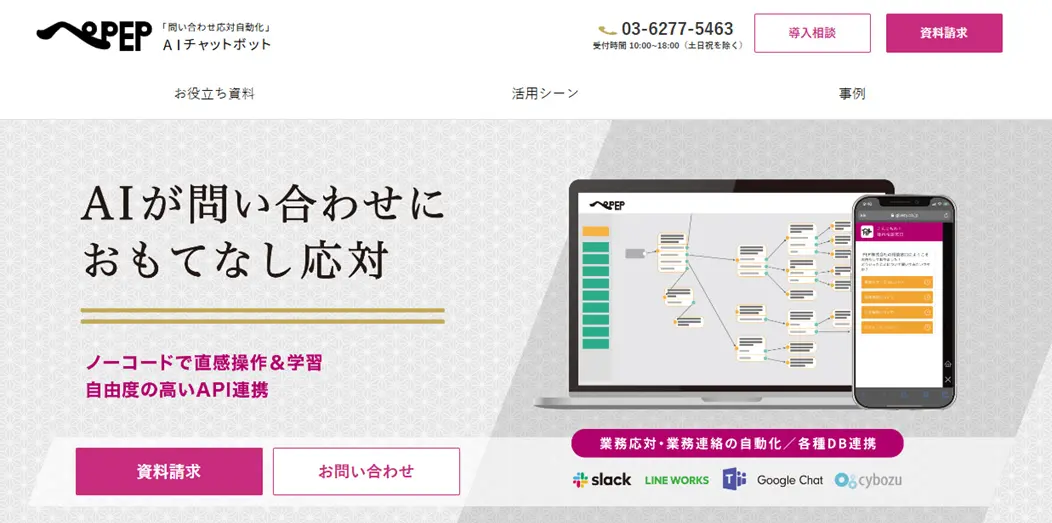社内ヘルプデスクの担当者は、社内から寄せられるさまざまな質問に対応します。しかし、別の業務と兼任している場合、業務負担が過剰になることも少なくありません。そこで活用したいのが「社内向けチャットボット」です。
本記事では、社内向けチャットボットの特徴や活用イメージ、導入のメリット、選定のポイントなどについて解説します。おすすめのツール11選も紹介するので、社内向けチャットボットの導入を検討している人はぜひ参考にしてください。
この記事でわかること
- 社内向けチャットボットのメリット
- 社内向けチャットボットの選び方
- 社内向けチャットボットのおすすめ10選
目次
社内向けチャットボットの特徴
チャットボットとは、チャット上でユーザーからの質問に自動返答するプログラムのことで、「社内受け」と「社外向け」に大別できます。
社内向けチャットボットは、その名の通り社内からの問い合わせに特化したものです。具体例としては、社内規定、マニュアル、FAQなどの情報を取り込むことで、社員からの質問に答えてくれる内ヘルプデスクとして活用することなどが挙げられます。
顧客からの問い合わせに特化した社外向けチャットボットと比較すると、社内向けチャットボットは、SlackやChatworkといった社内向けツールと連携しやすい傾向があります。
社内向けチャットボットの活用イメージ
社内向けチャットボットを導入した際の活用イメージをいくつかご紹介します。
まず、総務や人事などのバックオフィス業務での活用です。バックオフィス系の従業員は、「○○の場所はどこ?」などの簡単な質問を多くの人から受けることがあります。チャットボットを使うと定型化した質問にすぐに答えることができるため、よくある質問に対応する目的で導入されることがあります。
新入社員への社内ルールの教育にも利用できます。新人研修では社内ルールを一気に説明するのが一般的です。ただ、細かな項目は忘れてしまう可能性が高いので、チャットボット上で社内ルールをすぐに振り返れるようにすると、教育の手間の軽減につながります。
チャットからFAQに誘導するチャットボットを利用すれば、社内ヘルプデスクとしての役割を任せることもできます。チャットボットでは解決できない問題のみ有人対応することで、業務削減が可能です。
社内向けチャットボットを導入するメリット
社内問い合わせにチャットボットを活用すると、負担の軽減や業務効率化など、さまざまなメリットを受けられます。ここでは、チャットボットを導入することで得られる7つの効果をご紹介します。
社内ヘルプデスクの負担を軽減できる
チャットボットに社内ヘルプデスクの機能をもたせれば、社内ヘルプデスク担当者の負担を軽減することが可能です。
特に中小企業の場合、社内向けヘルプデスクを社内SEが兼任しているケースも珍しくありません。SEとして他の業務にあたっている際に社内からの問い合わせがあると、集中力が切れてしまうこともあるでしょう。にもかかわらず、社内ヘルプデスクには業務マニュアルを参考にすればすぐに答えがわかるような質問も多く寄せられます。
そこで、簡単な質問にはチャットボットが答えてくれるよう設定すれば、ヘルプデスク担当者が対応しなくても、社員が自己解決できるケースが多くなるでしょう。これにより、ヘルプデスク担当者の業務負担を大きく軽減することが可能です。
対応の質を均一化できる
問い合わせに人間が対応すると、質問の仕方によって回答が変わったり、ヘルプデスク担当者によって返答が異なったりすることがあります。チャットボットは同じ質問内容に対して、機械的に同じ回答をするため、担当者によるばらつきがなくなり、問い合わせ対応の品質が均一になります。
テレワークの推進につながる
社内ヘルプデスク業務を対面でのコミュニケーションで行っている場合、簡単な質問は近くの社員に聞けばすぐに解決できます。しかし、テレワークでは、質問者がチャットやメールで都度問い合わせる必要があり、テレワークの推進を妨げる要因になります。
チャットボットを導入すれば、多くの疑問を質問者が自己解決できるようになります。テレワークを導入しても業務効率を落とすことがないため、テレワークの推進を後押しする材料となります。
ヘルプデスクに情報が蓄積される
人力でヘルプデスク業務に当たる場合、社員から問い合わせのあった情報を管理できる態勢が整っていないと、ヘルプデスクに情報が蓄積されません。情報の属人化につながり、業務負担が増える可能性があります。
チャットボットは問い合わせを記録してデータベース化できるので、社内のナレッジを蓄積して集約できます。また、どういった質問が多いかを客観的に調査できるため、問い合わせ業務の改善も可能です。
質問者の回答待ちのストレスを軽減できる
チャットボットは質問に対して即座に回答します。人間が思考しながら答えるときのような待ち時間がないため、ユーザーはストレスを感じることなく課題を解決できます。
また、人間の担当者に質問する場合は、担当者の業務時間内でなければ回答を得られませんが、チャットボットなら24時間いつでも回答が可能です。
フレックス制をはじめとする自由度の高い労働時間制度を採用している企業では、「担当者と勤務時間が合わず、なかなか質問できない」という課題が発生しがちです。時間を問わずに質問できるチャットボットであれば、この課題も解決できるでしょう。
社内向けチャットボットを選ぶポイント
社内で利用するチャットボットは、顧客向けのチャットボットとは求められる機能が異なります。ここでは、社内チャットボットの選び方を5つ紹介します。
AI型でなくシナリオ型から選ぶのがおすすめ
社内チャットボットでは、人工知能(AI)は必要ない場合が多いです。これは、顧客を相手にする場合とは異なり、回答が難しいあいまいな質問をされる機会が少ないからです。
AIを搭載したチャットボットは、過去のやりとりのデータから自動で学習することで、あいまいな質問にも回答できるという長所があります。しかし、社内利用される場合は、よくある決まった質問に回答するケースが多いため、AIチャットボットの長所が発揮される機会が限られます。
また、AIチャットボットは、導入コストが高額になりがちです。費用対効果を考えると、社内利用の場合は、AIを使わないシナリオ型チャットボットが適しています。
AIチャットボットやシナリオ型チャットボットについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
オンプレミス型かクラウド型かを確認する
チャットボットは、大きく「クラウド型」と「オンプレミス型」の2つに分けられます。
クラウド型は完成したチャットボットをカスタマイズして作成するため、費用を抑えて導入が可能です。一方、オンプレミス型のチャットボットは一からチャットボットを作成するため、費用は高くなります。
しかし、オンプレミス型は、企業によって仕様を変更できるため、企業独自のセキュリティ要件を満たすことができます。社内にサーバーがある場合など、クラウド環境が使えない場合はオンプレミス型を選ぶ必要があります。
社内業務への導入事例があるかチェックする
チャットボットを選ぶ際には、自社に似た社内業務への導入事例があるかを確認しましょう。他社で導入実績があれば、社内利用に向いているチャットボットだと判断できます。
たとえ導入している企業が多いチャットボットであっても、顧客向けの用途にばかり使われているのなら、社内向けに使いやすいとは限りません。導入事例が不明な場合は、チャットボットを選定する段階で、提供元の企業に「社内利用の実績はありますか?」と確認するのが無難です。
サポート体制が充実しているか確認する
サポート体制が充実しているかどうかも重要なポイントです。チャットボットは導入後の改善が大切で、サポートを必要とする機会も多くなります。
チャットボットの提供会社は、改善のノウハウも持っています。そもそも自社だけで運用しようとせず、提供会社をうまく頼るようにしましょう。特に、AIを搭載したチャットボットが必要な場合、自社では手を加えられないケースが多いので、しっかりサポートしてもらえるかを念入りに確認してください。
無料で試せるかチェックする
無料で試せるチャットボットを選べば、導入のハードルを下げられます。実際に利用してみなければ、使いやすさや導入効果は判断しにくいため、手軽にいくつか試せるとベターです。
最初にお金を払って導入すると、たとえ使いにくくても「費用をかけたのだから変更したくない」という意識が働いてしまいます。無料でいくつか利用してみて、その中で良いものがあれば導入するというのも一手です。
チャットボットを試してみた結果、自社には合わないと感じる可能性もあります。その場合はチャットボットの導入は見送り、他の施策を検討しましょう。
おすすめの社内向けチャットボット11選
ここからは、チャットボットの中でも社内用としておすすめのものとして、以下の11個を紹介します。
- TETORI(テトリ)
- HiTTO(ヒット)
- 社内問い合わせさくらさん
- WisTalk(ウィズトーク)
- ふれあいコンシェルジュ
- OfficeBot(オフィスボット)
- Helpfeel(ヘルプフィール)
- PKSHA Chatbot(パークシャチャットボット)
- HRBrain AIチャットボット
- PEP(ペップ)
- My-ope office(マイオペオフィス)
TETORI(テトリ)
TETORI(テトリ)は、多彩な機能を備えたWeb接客ツールですが、社内向けチャットボットとしても十分な機能を有しています。管理画面は直感的に使いやすく、Web制作の知識がない担当者でもPDCAを素早く回せるでしょう。
無料トライアルではすべての機能を使うことができ、使用感をしっかりと確認できます。有料プランも月額1万円からと、リーズナブルな価格で利用可能です。
導入している機能は600社以上にのぼり、その業界も多岐にわたります。ITツールのレビュープラットフォーム「ITreview」におけるITreview Grid Award 2024 Fallでは、「Leader(リーダー)」もしくは「HIGH PERFORMER(ハイパフォーマー)」を3部門で獲得しており、高い評価を得ています。
| 初期費用 | 要問い合わせ (料金プランページへ) |
|---|---|
| 料金プラン | 要お問い合わせ(月額1万円~) (料金プランページへ) |
| 導入実績 | ホームページから確認可能 |
| 主な機能 | チャットボット 離脱防止ポップアップ ユーザー分析 シナリオ作成 ABテスト |
| 外部連携 | Googleアナリティクス 各種SNS |
| 無料お試し | 要問い合わせ (無料トライアルページへ) |
| 公式サイト | https://www.tetori.link/ |
HiTTO(ヒット)
HiTTOは、システムに関する知識がない人におすすめの社内向けAIチャットボットです。
2006年から数多くの企業データを分析し、社内情報の管理方法を最適化することで、社内問い合わせの対応工数を削減してきました。
実際に従業員から寄せられた質問の内容を蓄積し、利用状況の可視化もできるため、社内でよくある困りごとや疑問を解決しやすいのが特徴です。
| 初期費用 | なし |
|---|---|
| 料金プラン | 要問い合わせ |
| 導入実績 | ホームページから確認可能 |
| 主な機能 | オリジナルAI キャラクター設定 ダッシュボード 質問ログの蓄積 データの入出力 |
| 外部連携 | Microsoft Team LINE WORKS Google Chat Slack Chatwork |
| 無料お試し | 要問い合わせ |
| 公式サイト | https://hitto.jp/ |
社内問い合わせさくらさん

引用:社内問い合わせさくらさん
社内問い合わせさくらさんは、従業員の質問や疑問をスピーディに解決できる社内向けチャットボットです。
AIを搭載しており、問い合わせの履歴やPDFファイルや動画、画像など、あらゆる形式のデータを自動学習するため、利用するほど制度が高まります。
専任スタッフによる導入時のサポートと運用の支援も受けられるので、初めてのチャットボットとしてもおすすめです。
| 初期費用 | 要問い合わせ |
|---|---|
| 料金プラン | 要問い合わせ |
| 導入実績 | ホームページから確認可能 |
| 主な機能 | ビジネスチャット連携 有人チャット切り替え |
| 外部連携 | LINE Google Chat Slack Google Workspace Microsoft365 など |
| 無料お試し | 要問い合わせ |
| 公式サイト | https://www.tifana.ai/products/aichatbot |
WisTalk(ウィズトーク)
WisTalk(ウィズトーク)は、社内問い合わせ・ナレッジ活用に特化したAIチャットボットです。チャットボットで最も手がかかるQ&Aの作成をAIが行うため、運用の手間を大幅に削減できます。また、部門ごとのQ&Aのテンプレートも利用できます。
専任スタッフによって、導入計画から導後の回答精度の改善まで、手厚いサポートを一貫して受けられる点も魅力です。
| 初期費用 | 要問い合わせ |
|---|---|
| 料金プラン | 要問い合わせ |
| 導入実績 | ホームページから確認可能 |
| 主な機能 | 生成AI自動回答機能 Q&Aテンプレートの提供 Q&A登録機能 有人チャット機能 ダッシュボード機能 |
| 外部連携 | Microsoft Teams Microsoft SharePoint kintone Garoon |
| 無料お試し | あり |
| 公式サイト | https://www.panasonic.com/jp/business/its/wistalk.html |
ふれあいコンシェルジュ
ふれあいコンシェルジュは、ヘルプデスク担当者の負担軽減や、組織内のナレッジ共有に適した、AI搭載のチャットボットです。
ITスキルがなくても直感的に操作でき、導入時や運用中もサポートできるため、安心して利用を開始できるでしょう。また、社内向けに限らず、社外向けのサポートデスクとしても活用可能です。
| 初期費用 | なし |
|---|---|
| 料金プラン | 180,000円/月~ |
| 導入実績 | ホームページから確認可能 |
| 主な機能 | AI搭載FAQシステム FAQ登録アシスタント ファイル検索機能 承認機能 |
| 外部連携 | 要問い合わせ |
| 無料お試し | あり |
| 公式サイト | https://www.furecon.jp/ |
OfficeBot(オフィスボット)
OfficeBot(オフィスボット)は、組織内に蓄積されたデータから必要な情報を洗い出し、従業員の疑問を迅速に解消するチャットボットです。PDFやドキュメントなどの情報をアップロードするだけで、チャットボットの準備が完了する手軽さが魅力です。
独自のプロンプト調整により、あいまいな質問であっても適切な回答を返してくれるので、従業員がストレスなく利用できるでしょう。
| 初期費用 | 要問い合わせ |
|---|---|
| 料金プラン | 要問い合わせ |
| 導入実績 | ホームページから確認可能 |
| 主な機能 | 生成AIによる自動返答 |
| 外部連携 | Microsoft Teams Wow Talk Slack LINE LINE Works Google Shat |
| 無料お試し | あり |
| 公式サイト | https://officebot.jp/ |
Helpfeel(ヘルプフィール)
Helpfeel(ヘルプフィール)は、ユーザーのあらゆる問い合わせや質問表現に対応できるチャットボットです。社内規定やマニュアルをまとめて検索できるようになっているため、社内問い合わせに適しており、バックオフィス業務の効率化に適しています。
また、カスタマーサポートやマーケティング、DX推進といったさまざまなシーンで活用でき、社内と社外両方で利用したい企業にも向いています。
| 初期費用 | 要問い合わせ |
|---|---|
| 料金プラン | 要問い合わせ |
| 導入実績 | ホームページから確認可能 |
| 主な機能 | FAQ機能 チャットボット PDF(マニュアル)検索 |
| 外部連携 | 要問い合わせ |
| 無料お試し | 要問い合わせ |
| 公式サイト | https://www.helpfeel.com/ |
PKSHA Chatbot(パークシャチャットボット)
PKSHA Chatbot(パークシャチャットボット)は、ローコード・ローメンテナンスでカスタマーサポートや社内問い合わせを自動化できるチャットボットです。
ビックデータを活用した辞書データを搭載しており、あらかじめ会話の土台ができている状態からスタートするため、学習データが少なくても高い精度の回答を提示できます。
Office365やTeams、Slackといったツールとの連携も可能で、従業員にとって利用しやすいチャットボットといえるでしょう。
| 初期費用 | 要問い合わせ |
|---|---|
| 料金プラン | 要問い合わせ |
| 導入実績 | ホームページから確認可能 |
| 主な機能 | 学習する対話エンジン FAQ改善提案機能 有人チャット連携 SNS・チャットアプリ連携 |
| 外部連携 | Microsoft Teams Slack LINE LINE Works など |
| 無料お試し | 要問い合わせ |
| 公式サイト | https://aisaas.pkshatech.com/ |
HRBrain AIチャットボット
HRBrain AIチャットボットは、社内問い合わせ対応を自動化できるFAQシステムです。一般的な質問と回答に関するテンプレートが約500件も利用できるようになっています。
社内の問い合わせの傾向を可視化できるため、よりスムーズに回答内容のブラッシュアップができるのも魅力です。チャットツールとの連携も可能になっているため、利用を促しやすい点もメリットといえます。
| 初期費用 | 要問い合わせ |
|---|---|
| 料金プラン | 要問い合わせ |
| 導入実績 | ホームページから確認可能 |
| 主な機能 | 生成AIによる質問パターン自動生成 テンプレート機能 ダッシュボード機能 質問ログ機能 シナリオチャット 表記ゆれ対応機能 チャットツール連携 など |
| 外部連携 | Microsoft Teams Slack LINE Works など |
| 無料お試し | あり |
| 公式サイト | https://www.hrbrain.jp/assistant |
PEP(ペップ)
PEP(ペップ)は、社員や顧客からの問い合わせ対応を自動化できるAIチャットボット作成ツールです。管理画面はシンプルで、直感的に操作ができます。プログラミングも不要なので、ITスキルに自信のない担当者でも問題なく扱えるでしょう。
質問と回答の履歴を自動学習するため、利用するほど精度が高まります。メンテナンスにかかる工数が月に約2時間と短時間で済むのも嬉しいポイントです。
| 初期費用 | 要問い合わせ |
|---|---|
| 料金プラン | 要問い合わせ |
| 導入実績 | ホームページから確認可能 |
| 主な機能 | 選択肢型(シナリオ型)チャットボット作成機能 会話型(一問一答型)チャットボット作成機能 有人チャット連携型チャットボット作成機能 API連携機能 学習メンテナンス/会話分析機能 自然言語処理/PEP独自辞書 |
| 外部連携 | Microsoft Teams Slack LINE Works Google Chat など |
| 無料お試し | 要問い合わせ |
| 公式サイト | https://pep.work/ |
My-ope office(マイオペオフィス)
My-ope office(マイオペオフィス)は総務・人事部門に特化した、AI搭載型のチャットボットです。
管理画面のUIはシンプルで、ITに強い人材がいなくても運用できるでしょう。また、過去の対話履歴を閲覧でき、社内の課題の把握や、回答の精度向上にも活用できます。Microsoft TeamsやSlack、LINE Worksなど、社内で普段利用するツールとの連携も可能です。
| 初期費用 | 要問い合わせ |
|---|---|
| 料金プラン | 要問い合わせ |
| 導入実績 | ホームページから確認可能 |
| 主な機能 | 対話履歴の閲覧 24時間365日稼働 誰でも使える管理画面 質問サジェスト機能 CVSでのインポート |
| 外部連携 | Microsoft Teams Slack LINE Works Google Chat など |
| 無料お試し | 要問い合わせ |
| 公式サイト | https://www.my-ope.net/ |
社内向けチャットボットを導入する際のポイント
社内向けチャットボットを効果的に活用するためには、事前に検討しておくべきことがあります。ここでは、チャットボット導入を成功させるために考えておきたいポイントをご紹介します。
自社の規模に対してチャットボット導入が有効か見極める
数人〜数十人の従業員しかいない企業にチャットボットを導入すると、費用対効果が悪くなる可能性があります。社内コミュニケーションで課題解決に至るケースが多く、チャットボットの利用人数が少ないためです。
社内向けチャットボットを導入する場合、従業員100名以上を目安とすると良いでしょう。社員数が多ければ多いほどチャットボットの利用者は増え、問い合わせ担当者の業務効率化につながります。
目的・課題に沿った機能が搭載されているか確認する
せっかく導入するのだから、機能が充実したチャットボットにしたいと考える方もいるでしょう。しかし、自社にとって不要な機能が多くあっても、かえって使い勝手が悪くなってしまいます。「社内の課題を解決できるか」を念頭に置き、目的を明確にしたうえでそれに合ったものを選んでください。
社内のどの業務をチャットボットに任せるかを決めて機能を絞ることで、余分な費用がかからずコスト削減にもつながります。
運用担当者を決めて導入をすすめる
チャットボットの導入は、あらかじめ専任の担当者を決めたうえで進めるのが理想です。
導入を検討する段階では、チャットボットで解決したい課題を明確にしたうえで、その解決が期待できるツールを選定しなければいけません。また、導入するツールを決めた後も、シナリオの作成など、準備するべきことは多岐にわたります。その業務量は、従来の業務の片手間で行えるものではないでしょう。担当者が十分な時間を割けなければ、下調べやシナリオ設計が不足してしまい、当初期待した成果が得られない可能性があります。
チャットボット導入をスピーディに進め、その効果を最大化するためには、専任の担当者を任命し、チャットボット導入に集中できる体制を整えることが重要です。
社内向けチャットボット運用のコツ
ここからは社内向けチャットボット運用のコツとして、以下の3つを紹介します。
- 社員の目線に立って運用する
- 疑問を解決できない場合の対処法を用意する
- 継続した改善を行う
社員の目線に立って運用する
社内チャットボットは、「社員にとって使いやすくする」ことを強く意識し続けなければなりません。ここが抜けてしまうと、チャットボットの運用部署にとって都合のいいように、Q&Aを増やすだけになってしまう場合もあります。
チャットボットに組み込まれるQ&Aの数は、数値目標としてわかりやすいので、運用上のノルマとして設定されることがあります。しかし、ノルマを達成するために無駄にQ&Aの数だけ増やしても、社員の疑問は解決しやすくなりません。チャットボットの改善には、「どうすれば社員に価値を感じてもらえるか」という視点が不可欠です。
疑問を解決できない場合の対処法を用意する
チャットボットを利用しても疑問を解決できなかった場合に備えて、対処法を用意しておくことも大切です。チャットボットだけで社員の疑問をすべて解決するのは難しいので、社内ヘルプデスクなどへの電話・メールの問い合わせを簡単にできるようにしておきましょう。
チャットボット以外の対処法が用意されていないと、疑問を解決できなかった社員は不満を感じますし、そこで業務がストップしてしまう可能性もあります。利用フローを工夫しながら、効果的にチャットボットを活用してください。
継続した改善を行う
チャットボットの導入に失敗しないためには、継続した改善が欠かせません。社員が持つ疑問は会社によって違うため、会社の状況に合わせた改善をしなければ、チャットボットは未完成のままです。
社員がどんなことに困っているのかは、チャットボットの利用データを分析すれば見えてきます。素早く困りごとを解決できるように、チャットボットのシナリオを変更したり、足りないQ&Aを補ったりしましょう。
社内でチャットボットを活用しよう
今回は社内向けチャットボットについて解説しました。社内向けチャットボットには、ヘルプデスクの負担軽減やテレワークの推進など、業務効率化につながる多くのメリットがあります。また、チャットボットはただ導入するだけではなく、利用データを分析し、不足している内容を追加するなど、継続的な改善によって効果が高まります。
Web接客ツールのTETORIでは、月額1万円〜というリーズナブルな価格で、社内向け・社外向けのチャットボットを利用可能です。加えて、ポップアップや離脱防止、ABテストなど、さまざまな機能が搭載されています。
無料のトライアルも提供しているため、チャットボットの導入を検討している人は、ぜひお試しください。