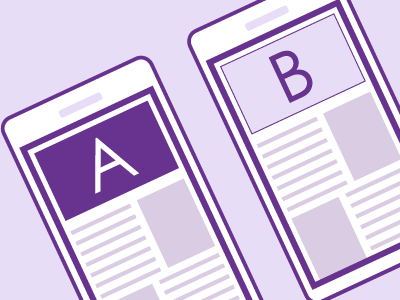サイトの離脱率の高さに悩んでいるマーケティング担当者の方は少なくありません。離脱率の改善は、高くなる原因を理解したうえで、適切な対策を取ることが重要です。
そこで今回は、離脱率を改善すべき理由を解説したうえで、高くなる主な原因や、具体的な改善策を紹介します。
この記事でわかること
- 離脱率を改善すべき理由
- 離脱率が高くなる原因
- 離脱率を改善するための施策
目次
離脱率を改善すべき理由
離脱率とは、そのページを最後にWebサイトから離脱したユーザーの割合を示す指標です。この離脱率を改善することで、サイト内の回遊をユーザーに促し、商品の購入やサービスの申込み、問い合わせ、資料請求といった、Webサイトの成果(コンバージョン)につなげることが可能です。
ここでは、離脱率を改善し、サイト内を回遊してもらえることのメリットについて詳しく解説します。また、離脱率が高くても問題ないケースについても、あわせて見ていきましょう。
サイト内を回遊してもらえることでさまざまなメリットがある
離脱率が高いページを改善し、離脱率を下げると、Webサイトの回遊率が高まります。回遊率とは、そのWebサイトを訪れたユーザー1人あたりのPV数を示す指標です。
回遊率を高め、サイトを訪れた人に多くのページを閲覧してもらえると、商品やサービスに対する理解が高まり、コンバージョンにつながりやすくなります。また、商品やサービスに愛着を持ってもらうことで、リピーター化やファン化を促すことも可能です。
また、離脱されにくいということはサイト内の滞在時間も長くなることでもあります。滞在時間が伸びると、ページ内で何かしらのアクションをするユーザーが多くなります。
離脱率の改善による回遊率や滞在時間の増加は、SEOの観点でもプラスになります。これにより、検索順位が伸び、自然検索流入の増加も期待できるでしょう。
このように、離脱率の改善はWebサイト全体の成果を考えるうえで、重要度の高い取り組みといえます。
離脱率が高くても問題ないケースもある
離脱率はコンバージョンへの影響が大きい要素ですが、離脱率が高くても問題ないケースもあります。
例えば、お役立ちコラムなどは、疑問を持って検索してアクセスし、コラムで疑問を解決したら離脱、という動きになりやすく、離脱率は高くなる傾向にあります。この場合、きちんとユーザーの悩みを解決できていればページの役割は果たしているため、離脱率が高くても問題ありません。
離脱率の改善が必要なページかどうかを見極め、改善が必要なページに適切に対処することが大切です。
離脱率が高くなる主な原因
離脱率を改善するためには、離脱率が高くなっている原因を把握する必要があります。離脱率が高くなる主な原因としては、以下の4点が挙げられます。
- 目的を達成できないと判断される
- 使いにくさによりストレスを与えている
- 外部サイトに誘導している
- 信頼できないサイトだと判断されている
それぞれ見ていきましょう。
目的を達成できないと判断される
サイトを訪れる人の多くは「情報を探したい」「買い物をしたい」などの目的を持っています。しかし、ユーザーが求める情報にすぐたどり着けないと「このサイトでは目的を達成できない」と判断され、離脱につながります。
つまり、サイトがターゲットを明確にできていなかったり、ユーザーのニーズを正しく把握できていなかったりすると、離脱率を高めるのです。
使いにくさによりストレスを与えている
ページが使いにくく、ユーザーにストレスを感じさせてしまうと、離脱率は高まります。
例えば、ページの表示速度は、離脱率を左右する要素の一つです。Googleの調査によると、ページの読み込みに3秒以上かかると、53%ものユーザーが離脱するとされています。
また、ユーザーが取るべきアクションが分かりにくかったり、サイト内の移動がスムーズにできなかったりしても、離脱率は悪化します。購入ボタンが目立たず見つけられない、関連記事へのリンクが分かりにくいといった小さな使いにくさが積み重なることで、離脱につながるのです。
現在ではかなり少なくなっているものの、レスポンシブデザインになっていないサイトもスマートフォンでの利便性が極端に落ちます。非対応の場合は優先的に対応したほうが良いでしょう。
外部サイトに誘導している
外部サイトへのリンクがクリックされると、ユーザーは自社サイトを離脱してしまいます。
一度外部ページへ遷移したユーザーは、元のページに戻ってくるのを手間だと感じやすい傾向にあります。明確な設置意図がある場合は別ですが、ユーザーを自社サイト内に留めておきたい場合は、外部リンクの取り扱いに最新の注意を払いましょう。
信頼できないサイトだと判断されている
サイト内に、ユーザーに不安を与える要素がある場合も、離脱率を高める原因となります。
例えば、掲載されている情報が古いままであったり、デザインが古めかしかったりすると、十分に管理されていないサイトだという印象をあたえ、信頼できないと判断されかねません。
そのほかにも、SSL化に未対応であったり、プライバシーポリシーが明記されていなかったりする場合も、セキュリティ面への不安から離脱することがあります。
ユーザーが安全に利用できるように工夫することが大切です。
離脱率を下げるための対策8選
ユーザーが離脱する原因がわかったところで、ここからは離脱率を下げるための対策として、以下の8個を紹介します。
- ポップアップを表示させる
- ページタイトルとページ内容をマッチさせる
- フォームの入力項目を減らす
- 関連性が高い内部リンクを厳選して設置する
- 視認性の高いCTAボタンでユーザーの行動を促す
- ページ表示速度を改善する
- こまめにサイトを更新する
- 企業情報を明記する
ポップアップを表示させる
Webサイトにポップアップを表示させると、離脱を防ぐ効果が期待できます。ポップアップとは、ユーザーがサイトを閲覧している途中に、画面上に小さなウィンドウやメッセージが表示される仕組みのことです。
ポップアップは一般的に、「お知らせ」や「クーポン」「メール登録の案内」など、特定の行動を促す目的で使われます。ページの本文とは別に目立つ形で表示されるため、ユーザーの関心を惹きやすいのがメリットです。
さらに、ポップアップは、タイミングを指定して表示できるという特徴があります。例えば、ユーザーが多く離脱する箇所に「今だけ10%オフクーポンを配布中」といったポップアップを表示すれば、離脱を防ぎ、サイトへの滞在時間を伸ばせる可能性が高まります。

すべての機能が利用できる無料トライアルが可能です。
ぜひご利用ください。
ページタイトルとページ内容をマッチさせる
離脱率を改善するには、ページタイトルとページ内容をマッチさせることが有効です。ユーザーはタイトルを見てからページを開いている場合が多いので、読者の期待に応えて離脱を防ぐためにタイトルと内容を一致させましょう。
例えば、「おすすめの温泉を紹介します」がページのタイトルなのに、ページ内に温泉とは関係のない情報ばかりが書いてあれば、すぐに離脱されてしまうでしょう。ページには「おすすめの温泉」の情報がまとめられていなければなりません。
すでにあるページを改善するのであれば、ページ内容を書き換えるよりも、タイトルを変更する方が簡単です。タイトルは訪問ユーザーを増やすためにも重要なので、じっくりと考えて決めましょう。
フォームの入力項目を減らす
フォームの入力項目を減らすことは、離脱率を改善するために有効です。フォームからの離脱が多い場合、ユーザーに「入力するのが面倒だ」と思われている可能性があるからです。
入力項目を減らせば、面倒だと思われにくくなるので、離脱率の改善が期待できます。特に住所を入力させる場合は入力項目が多くなりがちなため、項目数を必要最小限に絞りましょう。
購入や申込み用のフォームからの離脱が減れば、売上アップに大きな効果があります。フォームの見直しは優先して取り組みましょう。
関連リンク
関連性が高い内部リンクを厳選して設置する
離脱率を改善するためには、関連性が高い内部リンクを厳選して設置しましょう。サイト内の他のページに誘導できれば離脱を防げるからです。
内部リンクを設置するときは、やみくもにリンクを増やせばいいわけではありません。「元のページを見た人が、次に興味を持つことは何だろうか」と考えて、クリックされやすいリンクだけを置くことが大切です。
内部リンクが多すぎると、どれを選んでクリックすれば良いのかが判断できなくなり、ユーザーは何もクリックせずに離脱してしまいます。厳選した少数の内部リンクを設置することで、他のページも閲覧してもらえるよう促しましょう。
視認性の高いCTAボタンでユーザーの行動を促す
CTA(Call To Action)を工夫し、行動を明確に促すことも、離脱率改善に有効です。CTAとはユーザーに対して、商品やサービスの購入、会員登録、ダウンロード、お問い合わせといった行動を喚起する要素のことを指します。
購入ページや申込みフォームへたどり着いたユーザーは、コンバージョンに非常に近い状態です。しかし、この段階でCTAボタンが見つけにくかったり、次に取るべきアクションがわかりにくかったりすると、離脱を招き、貴重なコンバージョン機会を失ってしまいます。
CTAは、導線を目立たせるだけでなく、何をすべきかが直感的に伝わるように設計すると良いでしょう。「購入する」「申し込む」といった具体的なアクションを示す文言をボタンに含めると、ユーザーは次のステップを強く意識します。
また、飛ばし読みされても気づいてもらえるように、CTAボタンはページのなかでも特に視認性を高め、デザインにもメリハリをつけることが大切です。
適切なタイミングと場所にCTAを配置することで、離脱を防ぎ、コンバージョン率の向上につながります。
ページ表示速度を改善する
前述したように、ページ表示速度の遅さは、離脱率に直結します。まずはページの内容を見てもらえなくては、コンバージョンは達成できません。
表示速度を改善するにあたってまず取り組みたいのが、ページに使用されている画像や動画の最適化です。画像サイズを圧縮し、必要以上に大きなファイルを使用しないようにしましょう。不要な画像や動画を削除し、読み込み負荷の軽減を図るのも効果的です。
なお、表示速度に問題がある箇所は、Googleアナリティクスの滞在時間データから確認できます。また、PageSpeed Insightsを活用すれば、URLを入れるだけで表示速度を計測できるので、積極的に利用しましょう。
数値データをもとに表示速度を着実に改善していくことで、離脱率の低下とユーザー満足度の向上が期待できます。
こまめにサイトを更新する
掲載されている情報が古いままだと、ユーザーは「このサイトは放置されているのでは?」と不安を感じやすくなります。
例えば、会社の「新着情報」や「最新ニュース」の最終更新が何年も前から止まっている場合、そもそも企業が現在も存在しているのかといった疑念を抱かれかねません。
また、古い情報しか載っていない場合、「このサイトでは自分の悩みや疑問は解決できない」と判断されやすいため、離脱の可能性が高まります。
このような事態を防ぐために、定期的にコンテンツを見直し、必要に応じて最新情報を反映させることが大切です。信頼性と鮮度のあるサイト運営を行えば、離脱率低減につながります。
企業情報を明記する
Webサイトに企業情報を明記すれば、ユーザーからの信頼を獲得でき、安心して閲覧を続けてもらえます。その結果、離脱率の改善やコンバージョンの獲得が実現できるでしょう。
サイトに企業情報が記載されていないと、ユーザーがそのサイトに「この会社は本当に存在するのか?」「架空の詐欺サイトなのではないか」といった疑念を抱き、離脱してしまうリスクが高まります。この傾向は、特にECサイトや問い合わせフォームを設けているページで顕著です。
企業情報を記載する際には、企業名だけでなく、設立年、所在地、電話番号やメールアドレス、営業拠点、事業内容などを明記しましょう。これにより、「この企業は実在し、信頼できる運営元である」という安心感をユーザーに与えられます。
さらに、フォーム入力や資料請求などのアクションを促すには、プライバシーポリシーや個人情報の取り扱い方針を明記し、ユーザーが安心して個人情報を預けられる環境を整える必要があります。
離脱率改善に取り組む際のポイント
ここからは離脱改善に取り組む際に意識したいポイントとして、以下の2つを紹介します。
- 常にユーザー視点を持ち続ける
- データに基づいてPDCAを継続する
常にユーザー視点を持ち続ける
離脱率を下げるには、「ユーザーがどう感じるか」を常に意識することが大切です。
一般的に、ユーザーは自分が求める情報が見つからないと判断した時点でサイトから離脱します。例えば、以下のようなサイトは離脱を招きやすいでしょう。
- 内容がユーザーのニーズからずれている
- 情報量が不足している
- 情報量が多すぎて読みにくい
- 企業側の伝えたいことだけが記載されている
改善を図る際には、ユーザーの検索キーワードや行動データを分析し、どのようなニーズに応えられていないかを把握しましょう。そのうえで、必要な情報を過不足なく整理し、ユーザーが欲しい情報にすぐアクセスできるか、操作にストレスがないかを、常にユーザー視点で考える必要があります。
データに基づいてPDCAを継続する
離脱率の改善は、一度の施策で完了するものではありません。ある施策によって離脱率が改善したとしても、時間が経てばユーザーの行動やニーズは変化します。常に数値を確認し、PDCAを繰り返すことが、長期的な成果につながります。
PDCAを効果的に繰り返すためには、データツールの活用がおすすめです。例えば、ヒートマップなどのツールを使えば、どのページで離脱が多いのか、どの時間帯で離脱が発生しているのかを把握できます。また、ABテストも併用し、変更前後のバージョンで効果を比較することで、施策が本当に成果につながったかを客観的に検証できるようになります。
<。>データを活用して現状を正しく把握し、検証と実行を繰り返せば、的外れな対応を減らし、離脱率を効果的に改善できるでしょう
離脱率の改善方法まとめ
離脱率はWebサイトの成果に大きく影響する要素です。そのため、離脱率が高い場合はその原因を探り、離脱率を低くすることが重要です。
離脱率の継続的な改善に手が回らない場合は、外部ツールの導入がおすすめです。例えば、TETORIを利用すれば、業種に合わせたテンプレートによって、効果的にポップアップを表示できます。効果検証から改善までも簡単に行える点も魅力です。ぜひ一度お問い合わせください。