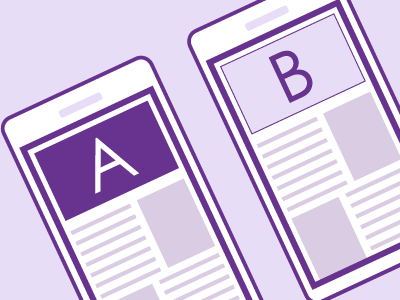「フォーム離脱率」とは、ユーザーが入力フォームで途中離脱してしまう割合のことを言います。CVR(コンバージョン率)、コンバージョン数に直結する重要な指標なので、きちんと理解したうえで改善に取り組みましょう。
今回は、フォーム離脱率の概要や、高くなる原因について解説したうえで、具体的な10個の改善策や、改善に向けたポイントなども紹介していきます。
この記事でわかること
- フォーム離脱率の意味や計算方法、平均
- フォーム離脱率が高くなる原因
- フォーム離脱率を改善するための方法
目次
フォーム離脱率とは
フォーム離脱率とは、Webサイトで入力フォームまで到達したユーザーが、最終的に入力を完了せずにフォームを離脱してしまう割合のことです。
この指標はCVRとの相関性が高い指標です。フォームで途中離脱しないということは=コンバージョンなので、フォーム離脱率が下がれば同時にCVRが上がります。
そのため、CVRの改善を目指すのであれば、フォーム離脱率の改善は優先的に取り組みたいポイントです。
フォーム離脱率の算出方法
フォーム離脱率は以下の式で計算できます。
フォーム離脱率(%)=フォーム離脱数÷フォーム訪問者数×100
例えば、フォーム訪問者数が200人で、そのうち80人がフォームを離脱した場合は、80÷200×100=40%という計算式になるため、離脱率は40%となります。
フォーム離脱率の平均値
フォーム離脱率は、一般的に40〜70%程度といわれています。ただし、フォームの目的やビジネスモデルによって大きく異なるため、明確な平均値はありません。
実際の調査として、株式会社ニュートラルワークスが実施した「問い合わせ・資料請求フォームにおける課題調査」では、約80%が「問い合わせ・資料請求フォームの入力中に離脱をした経験がある」と回答しています。
フォーム離脱率が高いとどうなる?
フォーム離脱率が高いと、CVRが低下し、ビジネスの成果に悪影響を及ぼします。
例えば、ECサイトの場合、購入手続きを完了しないユーザーが増えることになり、売上の損失につながるといえるでしょう。
また、問い合わせフォームの離脱率が高いと、リード(見込み顧客)獲得数が減少し、マーケティングの効果が薄れてしまいます。
このような事態を避けるため、定期的にフォーム離脱率を確認し、必要に応じて改善することが必要です。
フォーム離脱率が高くなる要因
フォーム離脱率が高くなる主な要因としては、以下の4点が挙げられます。
- 誤って入力フォームにたどり着いたユーザーが多い
- デザインが見にくい・使いにくい
- 入力に手間がかかる
- スマートフォンから操作しにくい
該当するものがある場合は、適切に改善を図りましょう。具体的な改善方法は次項で紹介します。
フォーム離脱率を改善する10個の方法
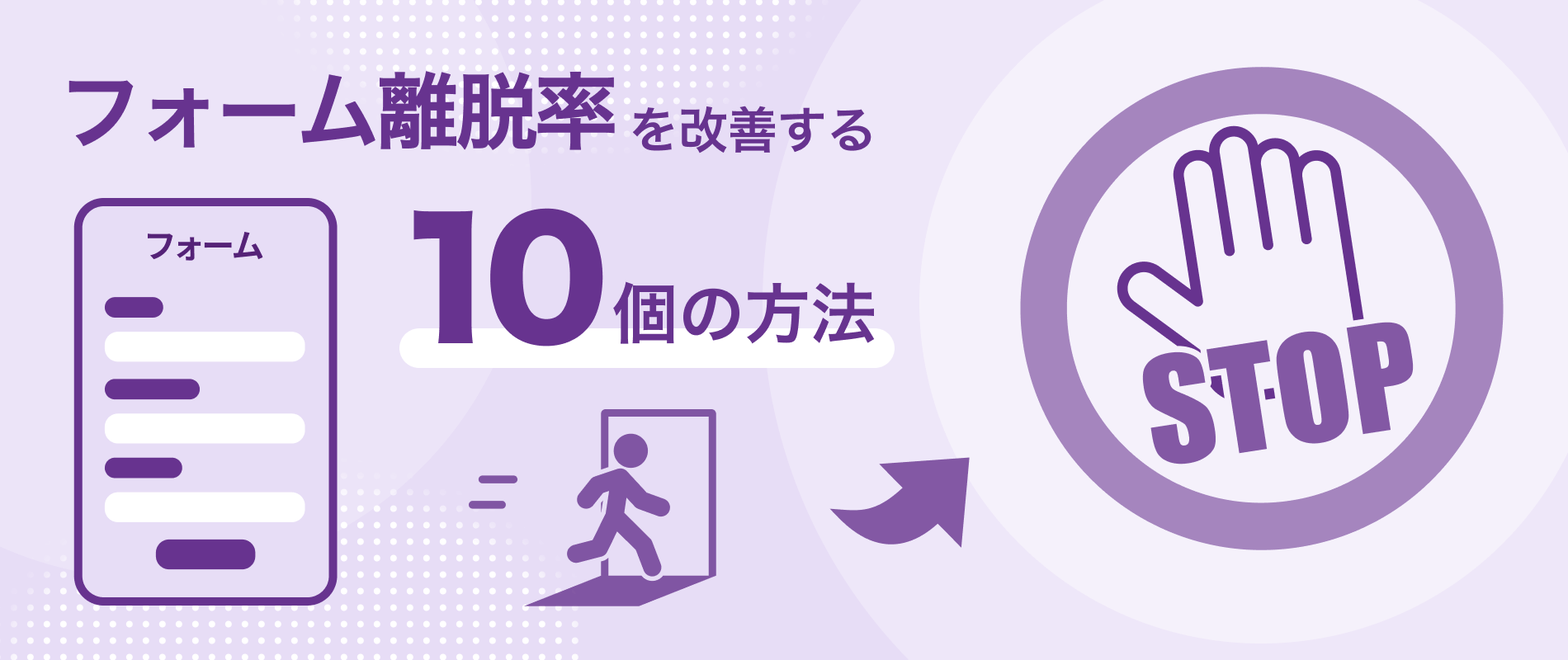
フォーム離脱率を改善する主な方法として、以下の10個を紹介します。
- 離脱防止ポップアップを表示する
- フォームの入力項目を絞り込む
- 入力アシスト機能を追加する
- 入力完了までのフローを可視化する
- フォームページ内に設置するリンクは最小限にする
- モバイル最適化を行う
- フォーム入力を途中保存できるようにする
- CTA(送信ボタン)を改善する
- チャットボットを活用する
- 安全性・信頼性を示す
それぞれ見ていきましょう。
離脱防止ポップアップを表示する
ユーザーがWebサイトを離脱しようとする際、ポップアップを表示して引き止める方法です。
具体的には、「まだ完了していません!このフォームを送信すると〇〇の特典がもらえます」といった、ユーザーにとってメリットのある内容を盛り込むのがおすすめです。
ただし、表現が過剰だったり、「閉じる」ボタンが見づらかったりすると、ユーザーの体験を損ね、逆効果となってしまう可能性もあります。
ポップアップを設置する際は、ユーザーの心情を考慮することが重要です。

すべての機能が利用できる無料トライアルが可能です。
ぜひご利用ください。
フォームの入力項目を絞り込む
フォームの入力項目を減らし、ユーザーの負担を減らすことも、フォーム離脱率の改善につながります。
入力項目が多いと、ユーザーが負担に感じ、フォームの途中で離脱する可能性が高まります。家族構成や電話番号などの内容は、本当に必要かどうかを検討し、不要であれば削ってしまったほうが良いでしょう。
また、必須項目と任意入力項目を明記することも、入力ストレスの軽減につながります。
入力アシスト機能を追加する
入力するべき内容がわかりにくかったり、エラーになったときにエラー箇所が特定しにくかったりすると、ユーザーはストレスを感じ、離脱する可能性が高まります。
以下のような入力アシスト機能を追加することで、入力時のストレスが軽減され、離脱率の低下が期待できます。
- 住所自動入力(郵便番号を入力すると住所が自動補完される)
- 入力例の表示(YYYY/MM/DDなどのフォーマット例を提示)
- リアルタイムエラーチェック(「このメールアドレスは無効です」などを即時表示)
入力完了までのフローを可視化する
「あといくつの項目を入力すればいいのか」「どれくらい時間がかかるのか」など、入力完了までのフローが可視化されていると、ゴールが明確になり、ユーザーは安心して入力を進められます。
「あと3ステップで入力完了」などのメッセージやフローバーを表示することで、離脱率の改善が期待できるでしょう。
フォームページ内に設置するリンクは最小限にする
フォームページ内に設置するリンクは、最小限に抑えましょう。
フォームページ内に他のページへのリンクが多いと、ユーザーの注意がそれてしまい、離脱につながる可能性が高まります。特にCTAボタン付近に不要なリンクを設置すると、ユーザーが誤ってクリックしてしまうことも考えられます。
ページが遷移した結果、また最初から入力しなおさなければならない事態に陥ると、ユーザーは入力を止めてしまうかもしれません。
FAQや補足情報を表示する場合は、モーダル表示にして、ページを遷移せずに解決できるようにするのがおすすめです。また、フォームページ内ではヘッダー・フッターのメニューが表示されないようにするのも効果的です。
モバイル最適化を行う
スマートフォンの普及により、スマートフォンからフォームを入力するユーザーが増えました。そのため、パソコンだけではなく、スマートフォンから操作しやすいように最適化することが重要です。例えば、以下のようなモバイル最適化を行うと効果的です。
- 入力欄の枠を大きくする
- 見やすい文字サイズに設定する
- タップしやすいボタンサイズにする
- 設問を縦一列に配置する
- 誤タップを防ぐために項目と項目の間を広くする
フォーム入力を途中保存できるようにする
フォームの入力内容は保存できるようにしておきましょう。入力中に離脱しても、再度訪問した際にその内容が保存されていれば、入力完了に至る可能性が高まります。
特に、入力内容を多くせざるを得ないフォームの場合、途中で入力を中断することが多く、最初から入力することになるとストレスが大きいため、途中保存の必要性は高いといえるでしょう。
CTA(送信ボタン)を改善する
CTAボタンは、資料請求や登録完了など、ユーザーの具体的な行動を後押しする役割があります。このCTAボタンのデザインや文言を工夫することで、フォーム送信をためらう人をフォローでき、離脱率の改善につながります。
具体的には、以下を取り入れるのがおすすめです。
- 文言を具体的にする(送信→無料相談を申し込む、登録を完了する、購入する)
- ボタンの色を目立たせる(背景とコントラストをつける)
- クリックしやすいサイズにする
チャットボットを活用する
近年普及が進んでいるチャットボットの導入も、離脱率改善に効果的です。
チャットボットはLINEなどのメッセージアプリに近い形式で利用できるため、ユーザーの心理的負担が少ないのが特徴です。入力ミスがあった場合もその場で優しく訂正を促してくれるため、ユーザーがストレスを感じにくい仕組みといえるでしょう。
上手く取り入れることで、離脱率改善につながります。
関連リンク
安全性・信頼性を示す
ユーザーによっては安全性や信頼性への不安からフォームを離脱することもあります。そのため、「入力した情報は安全に送信されるのか」といった疑問を解消することが離脱率の改善につながります。
以下のような情報を明記することで、入力した情報の取扱いやページの安全性を伝え、信頼性を示すと良いでしょう。
- SSL(https)を導入し、安全性をアピールする
- 「入力情報は第三者に共有されません」などのプライバシー表記を追加する
- 送信後の流れを明記する(例:送信後、24時間以内に返信します)
- 「お客様の声」「導入事例」「実績数」を入れる
- 会社情報(運営者情報・お問い合わせ先)を明記する
フォーム離脱率改善に取り組む際のコツ
ここからは、フォーム離脱率改善に取り組む際のコツとして、以下の3つを紹介します。
- シンプルで機能的なデザインを心掛ける
- EFOツールを導入する
- テストを行い効果を検証する
順番に見ていきましょう。
シンプルで機能的なデザインを心掛ける
フォームのデザインはできるだけシンプルにし、直感的に操作できるようにしましょう。
他社との差別化を図るあまり、フォームのデザインを複雑にしたり、奇抜にしたりすると、ユーザーは見づらさや使いづらさを感じ、ストレスの原因となる可能性があります。
ボタンを見やすくする、不要な装飾をなくす、適切に行間をあける、リンクを表示しないといった施策が効果的です。ユーザー目線で見やすく、使いやすいフォームにしましょう。
EFOツールを導入する
EFOツール(入力フォーム最適化ツール)を導入すれば、要件にあった入力フォームの作成をフォローしてもらえます。
たとえ担当者に専門知識がなくても、ユーザーの入力を支援する自動入力機能や、自動変換機能などを搭載した、最適なフォームを作成できます。
また、フォーム作成後も、入力にかかった時間やユーザーが離脱した箇所、ページの離脱率などを集計・分析できるため、施策の効果検証や改善点の特定も容易です。これにより、フォームの運営や管理の効率化を図れます。
テストを行い効果を検証する
フォームの改善では、施策が離脱率にどのような効果をもたらしているのか、正しく検証することが重要です。そこで有効なのが、A/Bテストを活用し、異なるフォームデザインや入力項目の構成を比較することです。
例えば、入力項目を減らしたバージョンとそのままのバージョンをテストし、どちらの離脱率が低いのかを測定するといった方法が考えられます。このようなテストを行い、継続的に改善を重ねることで、最適なパターンの特定が可能となります。
素早く効果的なA/Bテストを実施するには、「TETORI」を活用するのがおすすめです。
「TETORI」は、ポップアップやCTAの作成、分析ができるWeb接客ツールです。多種多様なテンプレートを用意しており、A/Bテストを素早く開始できるので、ぜひご利用ください。

すべての機能が利用できる無料トライアルが可能です。
ぜひご利用ください。
フォームの離脱率を改善するならTETORI
フォーム離脱率が高いと、売上の機会損失につながり、ビジネスの成果に悪影響を及ぼします。離脱率はさまざまな理由で高まるため、自社の状況に合った方法で改善を試みましょう。
「TETORI」では、関心の高いユーザーを取りこぼさないためのフォローアップ施策を行っています。前述したチャットボットやA/Bテストはもちろん、購入手続きに進んだユーザーの離脱時に購入特典を訴求するなどの対策も実施します。フォーム離脱率で悩んでいる方は、ぜひ「TETORI」をご活用ください。